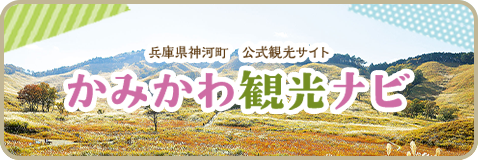介護保険サービス事業者の皆さまへ
- ページID:3023
- [更新日:]
ページ内目次
保険請求(月途中で区分変更等を行った場合)について
月途中に保険者が変更になった場合
月の途中で保険者が変更になった場合は、保険者番号・被保険者番号が変わるため、それぞれの期間に応じた請求明細書を、それぞれの保険者に請求します。また、居宅介護支援事業所の居宅介護支援費の請求および給付管理票の提出も、同様に、それぞれの保険者に請求します。
※支給限度額もそれぞれの保険者ごとに管理します。
月途中で要介護状態区分が変更になった場合
要介護⇔要支援の変更の場合、要介護と要支援の請求明細書の様式が異なるため、同じ被保険者番号をもつ利用者でも1月に請求明細書を2枚提出することになります。また、介護予防訪問介護などの月額報酬のサービスについては、月単位の報酬ではなく、日割計算用のサービスコードを使用して、対象となる期間分の日数を請求します。要介護度によって介護報酬が異なるサービスについては、サービス提供日ごとの要介護度に対応する報酬を算定することになります。
(例)4月10日に区分変更し、要介護1から要介護3に変更となった場合、4月9日までは要介護1に応じた単位数で請求し、4月10日からは要介護3に応じた単位数で請求します。
請求明細書(居宅介護支援費、介護予防支援費以外)
被保険者欄に入力する要介護(支援)状態区分・・・変更後(月末時点)の要介護(支援)状態区分
サービスコード・・・変更前後それぞれの要介護(支援)状態区分に応じたサービスコード
請求明細書(居宅介護支援費、介護予防支援費)
被保険者欄に入力する要介護(支援)状態区分・・・変更後(月末時点)の要介護(支援)状態区分
サービスコード・・・変更後(月末時点)の要介護(支援)状態区分に応じたサービスコード
※月途中で要支援⇒要介護に変更となった場合、介護予防サービス明細書と介護給付費明細書の2枚を提出し、明細書に記入する要介護状態区分は、2枚とも月末時点の介護度になります。
給付管理票
被保険者欄に入力する要介護(支援)状態区分・・・変更前後のいずれか重い方の要介護(支援)状態区分
支給限度基準額
変更前後のいずれか重い方の要介護(支援)状態区分に応じた支給限度基準額
プラン料の請求する事業所について
・月の途中で要支援から要介護に変更となった場合は、介護予防支援事業所から居宅介護支援事業所に移るため、月末時点に担当する居宅介護支援事業所が給付管理票を作成し、居宅介護支援費を請求します。逆に要介護から要支援になった場合は、月末時点に担当する介護予防支援事業所が給付管理票を作成し、介護予防支援費を請求します。
・介護予防サービスを利用する利用者が月途中で入院し、入院中に区分変更の申請を行い、要介護に変更となったが、その後の介護サービス利用がなかった場合は、介護予防支援事業所が給付管理を作成し、介護予防支援費の請求を行います。
・介護予防サービスを利用する利用者が月途中で要支援から要介護へ変更となり、小規模多機能利用へ変更となった場合は、介護予防支援事業所が小規模多機能型居宅居宅介護サービスを含めた給付管理を作成し、介護予防支援費の請求を行います。小規模多機能型居宅介護は日割計算用のサービスコードを使用して、対象となる期間分の日数を請求します。
・月途中で要介護2から要介護4へ変更となり、要介護4での介護サービスを受けていない場合の居宅介護支援費は、月末時点の要介護度の居宅介護支援費の請求を行います。
軽度者に対する福祉用具貸与の理由書について
軽度者(要支援1・2、要介護1)の人は下記の福祉用具は原則として保険給付の対象となりません。また、要支援1・2および要介護1・2・3の人は自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は原則として保険給付の対象となりません。
- 車いす(付属品を含む)
- 特殊寝台(付属品を含む)
- 床ずれ防止用具および体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
例外的に福祉用具貸与が利用できる場合
一定の条件に当てはまる場合は、介護保険での保険給付を受けることが可能です。
| 種目 | 一定の条件 | 判定方法 |
|---|---|---|
| 車いすおよび車いす付属品 | 次のいずれかに該当する者 ・日常的に歩行が困難な者 ・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | 基本調査1ー7「3.できない」 ケアマネジメントで判断 |
| 特殊寝台および特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 ・日常的に起き上がりが困難な者 ・日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1ー4「3.できない」 基本調査1ー3「3.できない」 |
| 床ずれ防止用具および体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3「3.できない」 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する者 (1)意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 (2)移動において全介助を必要としない者 | 基本調査3ー1「1.調査対象者が行けんを他者に伝達できる」以外または基本調査3ー2~3ー7のいずれか「2.できない」または基本調査3ー8~4ー15のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。 基本調査2-2「4.全介助」以外 |
| 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 次のいずれかに該当する者 (1)日常的に立ち上がりが困難な者 (2)移乗が一部介助または全介助を必要とする者 (3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | 基本調査1ー8「3.できない」 基本調査2-1「3.一部介助」または「4.全介助」 ケアマネジメントで判断 |
| 自動排泄処理装置 | 次のいずれにも該当する者 (1)排便が全介助を必要とする者 (2)移乗が全介助を必要とする者 | 基本調査2-6「4.全介助」 基本調査2-1「4.全介助」 |
医師の医学的所見に基づく例外的な給付について
下記に該当する者については、医師の医学的な所見とサービス担当者会議における適切なケアマネジメントにより、保険者が福祉用具貸与を認めることができます。
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって頻繁に前表の一定の条件に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
- 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに前表の一定の条件に該当することが確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から前表の一定の条件に該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作時等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
申請の方法
申請書類等

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
地域密着型サービスの市町村域を超えた利用について
地域密着型サービスとは
地域密着型サービスとは、要介護者等が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するものになります。
神河町には下記の事業所があります。
| 事業所名 | サービスの種類 | 定員 |
|---|---|---|
| 「さくら」グループホーム | 認知症対応型共同生活介護 | 9名 |
| グループホームゆうゆう | 認知症対応型共同生活介護 | 18名 |
| によん神河 | 小規模多機能型居宅介護 | 登録定員29名 (利用定員18名) |
| 地域密着型特別養護老人ホームうぐいす荘 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 29名 |
| デイサービス蓮 | 地域密着型通所介護 | 10名 |
| リハビリデイサービス心 | 地域密着型通所介護 | 10名 |
| デイサービスゆる結す | 地域密着型通所介護 | 13名 |
地域密着型サービスの利用について
神河町の被保険者が利用できる地域密着型サービスは、神河町内に所在する地域密着型サービスになります。他の市町村に所在する地域密着型サービスを利用したい場合は、市町村間合意の手続きにより利用することができる場合もあります。まずは、希望される利用者の保険者へご相談ください。
※市町村間同意の手続きは、利用者ごとに必要です。市町村間同意の手続きをせずに、サービス提供を実施した場合は、保険給付の対象外となりますので、ご注意ください。
他の市町村の地域密着型サービスの利用(例外的取扱い)について
神河町の被保険者が他の市町村に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合に、神河町が必要と認める基準は次のとおりとしております。
- 当該事業所の所在地が近隣市町村であり、神河町内に所在する地域密着型サービスの定員に空きがない場合
- 同一サービスを提供する事業所が町内にない場合
- 他市町村に在住する親族宅等に一時滞在する際に、他市町村の地域密着型サービスを利用する必要がある場合
- 虐待等のやむを得ない理由がある場合
住所地特例者の地域密着型サービスの利用について
住所地特例の対象施設に入所し、住民票も当該施設に異動している方は、住所地の市町村の以下の地域密着型サービスを利用することができます。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
※「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」および「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」は利用できません。
介護予防・日常生活支援総合事業に関すること
総合事業は、要支援者が利用する訪問介護、通所介護を全国一律の予防給付から市町村が地域の実情に応じて実施する地域支援事業に移行し、多様なサービスの充実を図る「介護予防・生活支援サービス事業」と、住民主体の介護予防活動の取組みを支援し、重度化予防を推進する「一般介護予防事業」で構成されています。
神河町では、平成29年4月から総合事業を実施しています。
| 事業名 | 対象者 | |
|---|---|---|
| 訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 事業対象者 要支援1・2 |
| 生活支援訪問サービス | 事業対象者 要支援1・2 継続利用要介護者 | |
| 通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 事業対象者 要支援1・2 |
| じっくり貯筋教室 | 事業対象者 要支援1・2 |
生活支援訪問サービスについて
事業の内容
神河町生活サポーターが利用者の居宅に訪問し、次に掲げる支援を行います。派遣回数は週2回までで、1回の訪問時間は45分以上1時間以内となります。
(1)食事の準備・片付け
(2)衣類の洗濯・補修
(3)居室等の掃除・整理整頓
(4)生活必需品の買い物
(5)その他必要な家事
*利用者本人への支援に限ります。
*身体介護を伴う支援は対象外になります。
手続の流れ
- 利用希望者は、ケアマネジャーと相談し、『神河町生活支援訪問サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)』を健康福祉課へ提出します。
- 町は、調査の上、利用の可否の決定し、利用希望者へ『神河町生活支援訪問サービス事業利用決定(変更・却下)通知書(様式第2号)』を通知します。
- 町は利用を決定した場合は、委託事業者に『神河町生活支援訪問サービス事業実施依頼(変更)通知書(様式第4号)』を通知します。
- 委託事業者は、利用者・ケアマネジャーと調整し、生活支援訪問サービスを提供します。
- 利用者は、委託事業者に利用料を支払います。
- 委託事業者は、生活支援訪問サービスの実施状況を町・ケアマネジャーへ報告します。
- 利用内容や回数を変更する場合は、利用者は『神河町生活支援訪問サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)』を健康福祉課へ提出します。
- 町は、調査の上、変更の可否の決定をし、利用者へ『神河町生活支援訪問サービス事業利用決定(変更・却下)通知書(様式第2号)』を通知します。
- 利用を中止する場合は、利用者は『神河町生活支援訪問サービス事業利用廃止(停止)届出書(様式第5号)』を健康福祉課へ提出します。
- 町は、委託事業者に『神河町生活支援訪問サービス事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第6号)』を通知します。
申請書類
注意点
- 生活支援訪問サービスは、限度額管理の対象となりますので、生活支援訪問サービスを含んだ支給限度額管理をしてください。ただし、給付管理においては、生活支援訪問サービスを除く給付管理票を作成し、国保連合会に送付してください。
- 3ヶ月以上入院する場合は、『神河町生活支援訪問サービス事業利用廃止(停止)届出書(様式第5号)』を提出してください。
サービスコード表・単位数表マスタ
遠隔地(町外)に居住する要支援者の取扱いについて
平成27年4月からの介護保険制度改正により、介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業等の利用が円滑に受けられるよう、要支援1・2の方のうち、住所地特例対象施設居住の住所地特例対象者の方で、居宅介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く)を受けられている方の担当地域包括支援センターが、すべて施設所在地の地域包括支援センターへ変更されました。また、総合事業を含めた地域支援事業についても、施設所在地の市町村が実施します。(平成27年4月施行)
※住所地特例対象施設
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
ケース1 神河町に住民票を置いたまま他市町村に居住している場合
本来は神河町の地域包括支援センターが予防プラン作成を行うことになりますが、遠隔地であるため、訪問などの実質的なプラン作成業務が困難です。その場合は、①神河町が居住地にある地域包括支援センターを「基準該当介護予防支援事業所」として登録し居住地の地域包括支援センターが実施する、②神河町地域包括支援センターが居住地にある指定居宅介護支援事業所に予防プラン作成業務を委託する、のいずれかの方法となります。
居住地に住民票を移すことで、行政からの書類などの郵便物が直接届くようになります。また、地域密着型のサービスなど居住地の自治体の制度やサービスを利用できるようになります。居住地での行政サービスが確実に受けられるよう、住民票の異動をご検討ください。
ケース2 ケアハウスやサ高住などに入居し、住民票を施設に移した場合
施設所在地の地域包括支援センターが担当します。また、総合事業を含めた地域支援事業についても、施設所在地の市町村が実施します。
ケース3 神河町に転入された要支援者の場合
転入前の市町村に住民票を置いている場合は、住民票のある市町村の方針に基づき、対応することとなります。まずは、住民票のある市町村の地域包括支援センターへご相談ください。
居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。神河町の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は、神河町の介護予防支援の指定を受ける必要があります。
事務フロー
指定居宅介護支援事業者が実施する指定介護予防支援の利用者が、予防給付の対象となる介護予防サービス等を利用しなくなった場合、当該利用者は第1号介護予防支援事業の対象となるため、当該利用者が引き続き当該居宅介護支援事業者による援助を受けようとする場合、センターが第1号介護予防支援事業の一部を委託する必要が生じます。
令和6年4月26日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡「指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について」を受け、次のとおりの流れとします。
主な指定要件等
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
- 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。
- 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能。
指定申請の方法
- 指 定 日 毎月1日
- 提出期限 指定(許可)を希望する月の前月20日
- 提 出 先 神河町健康福祉課 介護係
- 提出書類 (1)指定申請書
(2)付表 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項
(3)チェックリスト
(4)上記のチェックリストに示す添付書類
<注意事項>
〇法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
〇居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。
指定申請様式について
指定介護予防支援事業所の指定申請様式一式
必要書類の例示
必要書類の例示一式
高齢者虐待等にかかる通報について
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第5条において、高齢者の福祉に業務上関係のある団体や職員などは、高齢者虐待の早期発見に努めなければならないとされています。そして、同法第7条において、高齢者虐待を受けた思われる高齢者を発見した者は、速やかに通報しなければならないとされています。
居宅介護支援事業所の責務・役割
- 高齢者虐待(おそれ)を発見した場合は、速やかに地域包括支援センターへ連絡・通報します。
- 居宅介護支援事業所と高齢者本人、養護者との信頼関係の継続・強化を図ります。
- 高齢者虐待の改善に向けたケアマネジメントを実施します。
介護保険サービス提供事業者の責務・役割
- 高齢者虐待(おそれ)を発見した場合は、担当ケアマネジャーへ連絡・通報します。
- サービス利用時の高齢者の観察を行います。
- 高齢者や養護者の精神的な支援を行います。
- 利用者や家族からの苦情処理体制を整備します。
- 日頃から従事者に対する研修を実施します。
介護保険サービス事業者用権利侵害(おそれ)報告書書式
権利侵害(おそれ)報告書(事業所⇒神河町健康福祉課)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
高齢者虐待にかかる介護保険サービス事業者向け研修について
高齢者虐待の防止のためには、まず私たち一人ひとりが虐待に関する正しい知識を持ち、虐待を起させないよう、高齢者と養護者を支援していくことが大切です。高齢者虐待は、特定の人や家庭で起こるものではなく、どの家庭でも起こりうる身近な問題です。そして、介護のストレスが、高齢者と介護者の関係を悪化させ、虐待に至ってしまうケースも少なくありません。高齢者虐待防止法には、高齢者の保護とあわせて養護者への支援も盛り込まれており、その家庭に対してどのように支援することが望ましいのか、ともに考えていく姿勢が必要です。兵庫県では、下記の研修を開催しております。Off-JT研修の機会としてご活用ください。
高齢者虐待にかかる介護保険サービス事業所向け研修
 2025年度第2期 高齢者虐待対応力向上研修A研修 (PDF形式、270.51KB)
2025年度第2期 高齢者虐待対応力向上研修A研修 (PDF形式、270.51KB)介護保険サービス事業所の従事者向けでオンデマンド配信になります。
 2025年度 高齢者福祉施設職員向け研修 (PDF形式、221.90KB)
2025年度 高齢者福祉施設職員向け研修 (PDF形式、221.90KB)高齢者施設の従事者を対象とした、参集型とオンラインのいずれかを選択する研修になります。

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
福祉専門職対象防災対応力向上研修受講料の助成について
近年の度重なる自然災害では自力での避難が難しい、高齢者や障がい者といった「避難行動要支援者」と呼ばれる方々に、被害が集中しています。
平常時に要配慮者への支援を行われています、ケアマネジャーや相談支援専門員などの福祉専門職が、災害と災害のリスクを正しく理解し、福祉サービス従事者や地域住民・行政等と協力し、要配慮者に対する支援を行うための知識とスキルを身につけるとともに、避難のための「個別避難計画」を作成し、地域住民と共有するための実践力を習得することを目的とした研修会が開催されています。
神河町では、「個別避難計画」を作成できる福祉専門職を確保することを目的に、町内の事業所に勤務する福祉専門職1人につき1回限り、受講料の助成を行います。
対象となる研修

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
助成にかかる申請書類等
認知症介護実践研修(実践者研修)について
認知症加算の算定要件に該当する研修になります。市町推薦状が必要な場合は、申込〆切日に余裕を持って、介護保険係にご相談ください。
令和7年度申込期間
令和7年4月18日(金)から令和7年5月16日(金)正午まで
研修会場
西播磨総合リハビリテーションセンター 研修交流センター
住所:たつの市新宮町光都1-7-1
申込・問合せ先
西播磨総合リハビリテーションセンター研修交流センターのホームページをご覧ください。
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

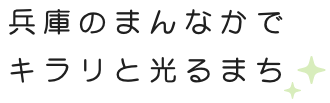
 くらし・手続き
くらし・手続き 子育て・教育
子育て・教育 健康・福祉
健康・福祉 しごと・産業
しごと・産業 町政情報
町政情報