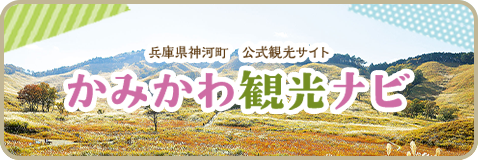【第1ステージ 第1回目】神河町議会のあり方ゼミナール
- ページID:3295
- [更新日:]
令和6年10月26日土曜日に第1回目の「神河町議会のあり方ゼミナール」を開催しました。
開催状況は下のとおりです。
第1回目の報告
第1回目ゼミナールの概要
- 日時:令和6年10月26日(土曜日)午前9時30分から
- 会場:大河内保健福祉センター2階 福祉講習室
- 受講者:ゼミナール生14名、神河町議会議員11名、市川町議会議員6名、福崎町議会議員1名
- 講師:長野県飯綱町議会元議長 寺島渉氏
- ファシリテーター:合同会社人・まち・住まい研究所 浅見雅之氏
- 内容:基調講演「議員のなり手不足対策と議会改革の推進」、パネルディスカッション「地方議会の現状と議会の役割」
第1回目ゼミナールの内容
澤田議長の開会挨拶後、長野県飯綱町議会元議長の寺島渉氏から「議員のなり手不足対策と議会改革の推進」と題して基調講演を聴講しました。
講演では、まず町村議員選挙の無投票、定数割れ団体は右肩上がりで上昇し、全国的になり手不足が課題となっている状況の説明がありました。
次に、無投票では住民の多様な意思・政策要求ができにくいことなど議員のなり手不足問題に潜むさまざまな危機があること、なり手不足解消には、議会に対する住民の関心を高めることが大前提であり、議会が取り組むべき事項は「多様な人が議員になるための環境整備(デジタル化、バリアフリー化、議員報酬の改善)」が必要であると話されました。
また、住民自治には住民の多様性を反映することが重要であり、議会選挙が無投票となった場合、住民の多様な意思・政策要求が確認できず、二元代表制(首長と議会)の機能が損なわれてしまい、議会の存在意義が薄れてしまいかねないとも発言がありました。
受講者は、真剣な表情で時折うなずきながら、寺島氏の講演を聴講していました。
基調講演後、人・まち・住まい研究所の浅見雅之氏がファシリテーターとなり、寺島渉氏、澤田俊一議長、小寺俊輔議会改革調査特別委員長と浅見氏を含めた4名によるパネルディスカッションを行いました。
まず、「無投票の危機感」について、澤田議長からは最初の選挙では自分に投じられた何百票という票が自分の発言の重みと感じていたが、無投票では自身への票=評価を得ることができず、4年間の取組の評価を選挙を通して受けたかったと発言がありました。
寺島氏からは、選挙でどれくらい票を得ることができるか、議員が頑張って活動すれば住民の方は評価し票を伸ばせる。それは議員の自信にもつながる。一方で、無投票は周りの人が評価しないような方でも議員にしてしまうと話されました。
そのほか、議員間討議や議員と住民の対話について、うまくディスカッションができていないことなどが出される中で、ファシリテーターの浅見氏からは、自由に話せる条件が満たされれば、「みんなが語りだす」と提起。その条件は語り合う安全であり、話し合う「安全・安心の場」があれば住民と議員のコミュニケーションを作り出せると話されました。
最後に、地域の中は男性が集落の役員を担う現状も出される中で、寺島氏からは、地元で活発に活動する70代の女性が自治会の総会で「嫁に来て50年、初めて自治会の総会に参加し、自治会のいろんなことがこの総会で決まっていることを知った」と話されたことに端を発し、以後は男女が総会に参加するなど自治会のあり方を考えるきっかけとなったと話されました。
これからは情報をオープンにし、話し合いの中に変革のヒントがある。そのことに気づかせていただきました。
最後に、栗原副議長より閉会の挨拶があり、「次回のゼミナールは『こんな議員は嫌だ』をテーマにゼミナール生のみで意見交換を行います。意見交換はゼミナール生のみですので、皆さん忌憚のないご意見を出してください。」とゼミナール生に声掛けがありました。
閉会挨拶後、あり方ゼミナールの開催を記念し、ゼミナール生と議員で記念撮影を行い、第1回目の議会のあり方ゼミナールは終了しました。
第1回目あり方ゼミナールの資料はこちら
お問い合わせ
神河町役場議会事務局
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎3階)
電話番号: 0790-34-0213 ファックス番号: 0790-34-0034

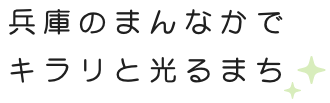
 くらし・手続き
くらし・手続き 子育て・教育
子育て・教育 健康・福祉
健康・福祉 しごと・産業
しごと・産業 町政情報
町政情報