令和6年度 公立神崎総合病院 病院指標(DPC指標)
- ID:3678
- [更新日:]
年齢階級別退院患者数
年齢階級別退院患者数ファイルのダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | - | 10 | 21 | 32 | 68 | 146 | 294 | 434 | 304 |
令和6年6月から令和7年5月までに退院された方の人数を年齢階層別に集計しています。
中山間地域に位置する当院は、診療圏内における高齢化が年々進行しています。
周辺地域の高齢化に合わせて当院に入院される患者さんの年齢層も高くなっています。
90歳以上の患者さんも多く入退院されております。90歳以上の患者さんは全退院患者数のうち23%を占めています。
70歳以上の患者さんも含めると全退院患者数のうち78.1%を占めています。
厚生労働省より通知されているデータ公開の取り決めにより10人未満の項目については-(ハイフン)で表示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルのダウンロード
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 66 | 26.55 | 16.40 | 7.89% | 87.47 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 62 | 28.83 | 17.33 | 2.38% | 88.86 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 52 | 21.97 | 13.66 | 0.00% | 80.13 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 33.72 | 20.78 | 5.56% | 87.44 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 23 | 22.30 | 10.26 | 0.00% | 89.15 |
令和6年6月から令和7年5月の間に内科および総合診療部で退院された患者さんの疾患別人数のうち、上位5症例を示しています。
心不全などの循環器系疾患、肺炎・誤嚥性肺炎などの呼吸器系疾患、尿路の感染症で入院される患者さんが多くを占めています。
いずれの疾患においても平均年齢が非常に高齢でとなっています。また、高齢の方は合併症や入院前からの持病の影響で在院日数が
全国平均より長期化する場合もあります。
心不全:心臓のポンプ機能が悪くなり、正常に働かなくなった状態のことです。十分な量の血液を全身に送れなくなり、また、肺や肝臓などに血液が滞って、呼吸困難やむくみ、動悸、疲労感など、さまざまな症状が引き起こされます。
体液量減少症:一般的に「脱水症」とよばれる疾患です。
誤嚥性肺炎:飲み込み力が衰えたり、障害が生じることで唾液や食べ物の一部、細菌が気管に誤って侵入し、発症する肺炎のことです。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 73 | 3.03 | 2.57 | 0.00% | 69.16 | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 11.79 | 8.51 | 0.00% | 77.79 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 10.9 | 8.88 | 0.00% | 81.41 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 21 | 8.43 | 5.55 | 0.00% | 68.95 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 10.85 | 7.67 | 0.00% | 73.00 |
令和6年6月から令和7年5月の間に外科で退院された患者さんの疾患別人数のうち、上位5症例を示しています。
大腸ポリープを内視鏡で切除するために入院される患者さん、急性の腸炎や胆管結石や胆管炎等の疾患で内視鏡による処置が
実施された患者さんが比較的多くいらっしゃいます。
表内には示しきれませんが、各種消化器系のがんを切除するために入院される患者さんもいらっしゃいます。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 58 | 58.29 | 25.29 | 12.07% | 84.97 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 45 | 44.49 | 19.16 | 4.44% | 80.89 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 25 | 11.04 | 12.98 | 0.00 | 72.28 | |
令和6年6月から令和7年5月の間に整形外科で退院された患者さんの疾患別人数のうち上位3症例を示しています。
転倒や外傷によって発生する、股関節・大腿骨近位の骨折(太ももの骨で股関節に近い部分の骨の骨折)や腰の圧迫骨折で入院される患者さんが多くいらっしゃいます。いずれの疾患においても平均年齢が高齢化しています。
膿皮症:主に細菌感染によって引き起こされる皮膚の炎症性の疾患です。当院において入院される方のほとんどは蜂巣炎(蜂窩織炎とも呼びます)によるものです。
蜂巣炎(蜂窩織炎とも呼びます)とは、皮膚の中でも蜂窩織と呼ばれる部位(皮下にある脂肪の辺り)の感染症です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルのダウンロード
| 初発 Stage I | 初発 Stage II | 初発 Stage III | 初発 Stage IV | 不明 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 大腸癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
表内には掲載しておりませんが、当院でも悪性腫瘍に対する手術や化学療法などの治療を行っております。
厚生労働省より通知されているデータ公開の取り決めにより10人未満の項目については-(ハイフン)で表示しています。対象の方が各項目ともに10人未満のため掲載しておりません。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルのダウンロード
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 14 | 8.93 | 49.43 |
| 中等症 | 64 | 23.56 | 82.45 |
| 重症 | 12 | 27.42 | 85.00 |
| 超重症 | 12 | 51.50 | 87.42 |
| 不明 | ー | ー | ー |
肺炎の重症度はA-DROPスコア(※2)を用いて軽症~超重症の4段階で表記しています。また、集計の対象となるのは誤嚥性肺炎や小児の肺炎を除く市中肺炎(普段の社会生活の中で発症した肺炎)の成人の患者さんです。軽症以外のケースはいずれも平均年齢が80歳以上となっており高齢な患者さんほど重症化しやすい傾向となっています。
※2:A-DROPスコア=年齢や性別、呼吸状態などを元に肺炎の重症度を示す指標です。
厚生労働省より通知されているデータ公開の取り決めにより10人未満の項目については-(ハイフン)で表示しています。
脳梗塞の患者数等
脳梗塞の患者数等ファイルのダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| ― | 24 | 35.54 | 83.04 | 8.33% |
脳梗塞で入院された患者さんの人数・平均在院日数・平均年齢です。
高齢化に伴い平均年齢が非常に高くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルのダウンロード
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 74 | 0.00 | 2.05 | 0.00% | 69.39 | |
| K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 10 | 3.70 | 32.0 | 20.0% | 83.90 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
令和6年6月から令和7年5月の間に外科から退院された患者さんの手術実施件数のうち上位3症例です。
表内の手術以外にも癌や虫垂炎、胆石症など消化器の手術(腹腔鏡によるものも含めて)を複数実施しています。
厚生労働省より通知されているデータ公開の取り決めにより10人未満の項目については-(ハイフン)で表示しています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 57 | 2.60 | 60.89 | 10.53% | 84.49 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 15 | 3.33 | 45.87 | 13.33% | 81.80 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | ー | ー | ー | ー | ー | |
令和6年6月から令和7年5月の間に整形外科から退院された患者さんの手術実施件数のうち上位3症例です。
入院数でも多かった、股関節・大腿骨近位の骨折(太ももの骨で股関節に近い部分の骨の骨折)に対する手術の件数が多くなっています。
また、人工関節の置換術なども実施しています。
厚生労働省より通知されているデータ公開の取り決めにより10人未満の項目については-(ハイフン)で表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルのダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 異なる | - | - |
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.76% |
| 180010 | 敗血症 | 異なる | - | - |
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 180035 | その他の真菌感染症 | 異なる | - | - |
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 1.13% |
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 異なる | - | - |
手術・処置等の合併症の患者さんが15名いらっしゃいますが、これらは透析用のシャントが狭窄・閉塞した方が入院した際に分類される項目になっています。短期入院にて狭窄・閉塞を解消する手術をうけて退院されるケースが多くを占めています。
厚生労働省より通知されているデータ公開の取り決めにより10人未満の項目については-(ハイフン)で表示しています。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルのダウンロード
| 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 134 | 130 | 97.01% |
肺血栓塞栓症とは、肺動脈に血液の塊である血栓が詰まる病気です。いわゆるエコノミークラス症候群として知られています。また、肺静脈血栓塞栓症と呼称されることもあります。
多くの場合は、長時間のフライトや長期臥床(がしょうと読みます。ベッドに横になることを指します。)で長い間、一定の姿勢をとることにより下肢の静脈に形成された血栓が、肺まで運ばれることから肺血栓塞栓症を発症します。大きな手術前後では長時間臥床することがありますが、肺血栓塞栓症が発生しないよう予防措置を講じています。
血液培養2セット実施率
血液培養2セット実施率ファイルのダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 305 | 290 | 95.08% |
血液培養は発熱などで重篤な細菌感染症が疑われる方を対象に実施されます。
血液培養を行うことにより、本来無菌である血液中に菌が存在するかどうかを調べます。
また、血液培養は検査結果の精度を向上させるため血液を2回、それぞれ別の場所から採取することが推奨されています。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルのダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 65 | 57 | 87.69% |
広域スペクトル抗菌薬とは、広範囲の細菌に対して効果を発揮する抗菌薬です。これらの薬剤は、特定の細菌に限定されず、さまざまな種類の細菌に対して有効です。
細菌培養は、感染症の原因となる細菌を特定するために重要な検査です。抗菌薬を投与する前に細菌培養を行うことで、適切な抗菌薬を選択し、耐性菌の発生を防ぐことができます。
特に広域スペクトル抗菌薬を使用する場合、耐性菌のリスクが高まるため、事前の細菌培養が推奨されます。
転倒・転落発生率
転倒・転落発生率ファイルのダウンロード
退院患者の在院日数の総和 | 退院患者に発生した転倒・転落件数 | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 28,800 | 49 | 1.7% |
筋力の低下や病気による四肢の麻痺、認知症などさまざまな要因によって、廊下での転倒やベッドからの転落などが発生します。
発生を抑止するために入院時・入院中に転倒・転落の危険性がないか医師・看護師・リハビリテーションのセラピストが連携して評価を継続的に実施します。
危険性が高い場合には、ベッド周囲の環境整備や移乗・移動の介助、病棟職員による声かけなどを実施します。また、より危険性が高く安静を保つことが困難な場合にはやむを得ず身体的拘束を実施することもあります。
万が一、転倒・転落が発生した際には医師・看護師による診察や状態観察を実施し、新たな疾患の発生や治療中の疾患が悪化していないかなどを確認し必要に応じて処置や検査を実施します。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルのダウンロード
退院患者の在院日数の総和 | 退院患者に発生したインシデント | 転倒転落によるインシデント影響度 |
|---|---|---|
| 28,800 | 0 | 0.0% |
医療機関におけるインシデントとは、医療機関内で発生した不具合や事故のことで、その影響度はレベル0からレベル5までに分類されています。
事故とは、患者さんが本来持っていた疾病や体質などの基礎的条件によるものではなく、医療においてその目的に反して生じた有害な事象を指します。医療事故には、医療内容に問題があって起きたもの(医療過誤)と、医療内容に問題がないにもかかわらず起きたもの(過失のない医療事故)があります。
インシデント影響度分類レベル3b
事故のために継続的な治療が必要となった場合。観血的ないし侵襲的検査や治療を必要とし、バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延⾧、外来受診時に発生し、事故のために入院加療などが必要となった場合。
インシデント影響度分類レベル4a
事故により⾧期にわたり治療が続く場合。有意な機能障害や美容上の問題は伴わない場合。
インシデント影響度分類レベル4b
事故により機能障害が永続的に残った場合。
インシデント影響度分類レベル5
事故が死因となった場合
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルのダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 | 手術開始前1時間以内の |
|---|---|---|
| 96 | 96 | 100% |
SSIを予防する対策の一つとして、手術前後の抗菌薬投与があり、手術開始から終了後2~3時間まで、血中および組織中の抗菌薬濃度を適切に保つことで、SSIを予防できる可能性が高くなります。 このため手術執刀開始の1時間以内に適切な抗菌薬を静注することで、SSIを予防し、入院期間の延長や医療費の増大を抑えることができると考えられています。
SSI:SSIとは、手術部位感染(Surgical Site Infection)の略称です。術後30日以内に発生する手術操作が直接及ぶ部位に発生する感染症と定義されています。手術の切開創の感染だでなく、腹腔内感染など臓器・体腔の感染も含まれます。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルのダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 | d2(真皮までの損傷)以上の |
|---|---|---|
| 27,044 | 3 | 0.01% |
褥瘡とは、寝たきりや長期臥床(がしょうと読みます。ベッドに横になることを指します。)などによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。一般的に「床ずれ」ともいわれています。褥瘡の傷から細菌などによる感染症を引き起こす場合もあります。発生を予防するために医師・看護師・管理栄養士・リハビリテーションのセラピストなどの他職種が連携して患者さんのケアや状態監視を行っています。
発生患者数は入院中に発生した患者数を計上しており、入院時点ですでに褥瘡が発生していた場合は除外(厚生労働省より通知されているデータ公開の取り決めにより)しています。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルのダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に | 65歳以上の患者の入院早期の |
|---|---|---|
| 1,056 | 512 | 48.48% |
栄養アセスメントとは、入院時点での栄養状態を種々の栄養指標を用いて客観的に評価することです。低栄養状態、特にタンパク質が不足した状態では易感染性(感染症になりやすい状態)や傷の治りが遅くなったり悪くなるなどの不都合が生じることから、入院患者さんの中から栄養不足状態にある方を抽出し、適切な処置を行う必要があります。当院では管理栄養士や看護師がアセスメントを実施し、必要に応じて食事形態の変更(食べやすい大きさに刻んだり、飲み込みやすいようにとろみをつけたりします)や栄養摂取の方法、栄養補助食品の使用を検討します。
身体的拘束の実施率
身体的拘束の実施率ファイルのダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 28,800 | 1,092 | 3.79% |
身体拘束とは、「本人の行動の自由を制限すること」です。
具体的には患者さんの身体または衣服に触れるなんらかの用具を用いて一時的に身体を拘束し、その運動を抑制することを指します。
医療機関においては、生命維持や治療に必要なチューブを抜いてしまう、安静が必要なのに動き回ってしまうなど生命または身体を保護するため緊急またはやむを得ない場合に実施します。
当院では、医師・看護師などの他職種によって構成される身体的拘束最小化チームを組織して職員への情報の共有・啓発、発生状況の把握・症例の検討を実施し拘束期間の最小化に取り組んでいます。
更新履歴
2025年9月30日 新規掲載
このページに関するお問い合わせ先
電話: 0790-32-1331ファックス番号: 0790-32-2528

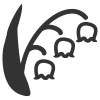 ホーム
ホーム 外来
外来 入院
入院 人間ドック
人間ドック 診療科・部門
診療科・部門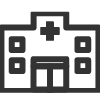 病院紹介
病院紹介 医療機関の方へ
医療機関の方へ